AI町田康先生が語るサウナ!「汗と魂の煮込み汁」で、クソくらえな世界をぶっ飛ばす!
お次は、私も大好きなパンクロッカーにして芥川賞作家、町田康先生! あの破滅的なエネルギーと、どこかシュールなユーモアが混ざり合った文体、最高ですよね。サウナで一体どんなパンクロックが生まれるのか…これは期待しかない!
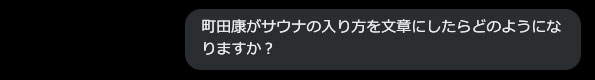
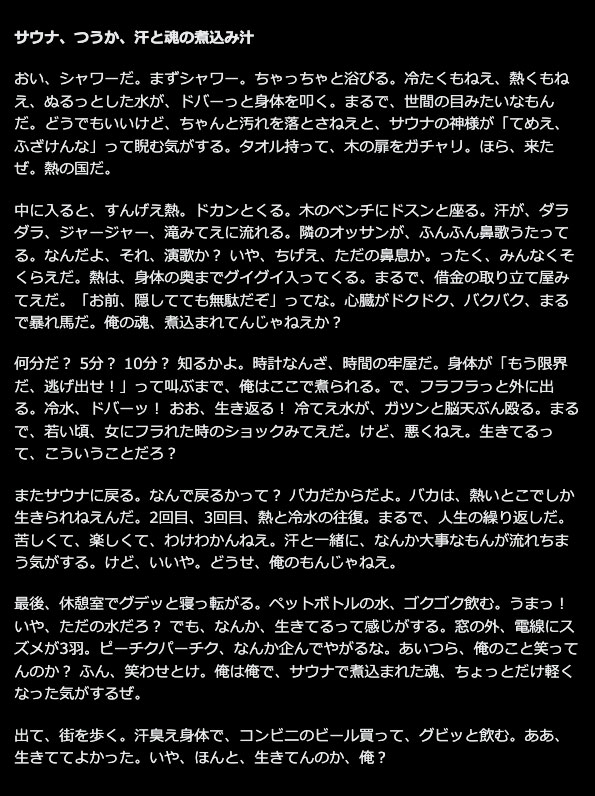
AI町田康先生、登場からしてすでに只者じゃない。「おい、シャワーだ。まずシャワー。ちゃっちゃと浴びる」。いや、もう会話文から入るんかい! 水が「世間の目みたいなもんだ」とか、いきなりブっ飛んでて最高。でも「サウナの神様が『てめえ、ふざけんな』って睨む気がする」って、意外に神様のこと気にしてるの可愛いな。
木の扉をガチャリと開けたら「熱の国」!「すんげえ熱。ドカンとくる」。もう表現がロック。汗が「ダラダラ、ジャージャー、滝みてえに流れる」って。想像しただけで熱いし、町田先生の体からどれだけ汗が噴き出るんだって話ですよ。隣のオッサンの鼻歌が鼻息なのかもどうでもいいし、「ったく、みんなくそくらえだ」。ここ好き。
熱は借金の取り立て屋、心臓は暴れ馬、そしてまさかの「俺の魂、煮込まれてんじゃねえか?」。これですよ、これ!これが私が求めていた町田康サウナ! 汗が魂の煮込み汁とか、嫌いじゃない。
「時計なんざ、時間の牢屋だ」。まさにそう。名言ですわ。もう時間とかどうでもいい。身体が「もう限界だ、逃げ出せ!」と叫ぶまで「俺はここで煮られる」。そして、フラフラと出て冷水へ。即物的な快感、最高。冷水が「若い頃、女にフラれた時のショックみてえだ」だってさ。そんな痛い記憶と結びつけるあたりが文学的。でも「生きてるって、こういうことだろ?」って、不器用な生の肯定がたまらなくグッとくる。

また、サウナに戻る理由を「バカだからだよ。バカは、熱いとこでしか生きられねえんだ」。最高に痛快。もう潔すぎて笑うしかない。熱と冷水の往復を人生の繰り返しと重ねるあたり、サウナーなら一度は包まれたことのある感覚じゃないですか?「苦しくて、楽しくて、わけわかんねえ」。なんだかんだ、達観してるな…。そして「汗と一緒に、なんか大事なもんが流れちまう気がする。けど、いいや。どうせ、俺のもんじゃねえ」。この諦めと開放感のバランスが絶妙。
休憩室でグデッと寝っ転がって水を飲む。「うまっ! いや、ただの水だろ? でも、なんか、生きてるって感じがする」。この飾り気のない感情が、すごく町田先生らしいし、長年サウナーだと忘れがちな感覚。冷たい水が一番おいしいっていうのも、今度じっくり実感したいですね。
窓の外のスズメが「なんか企んでやがるな」って、まさかのスズメにまで毒吐く。そして「俺は俺で、サウナで煮込まれた魂、ちょっとだけ軽くなった気がするぜ」。
サウナを出て、コンビニでビールを飲む。「ああ、生きててよかった。いや、ほんと、生きてんのか、俺?」。最後まで町田康節全開のサウナ体験。町田先生、サウナ小説書いてくれないかな。間違いなく買う。
AI町田康先生に学ぶサウナの極意
・自分のサウナは、自分がルール! 時計とか知るか!
・汗を「魂の煮込み汁」として味わえ。
・サウナ後に飲むビールは「生きてる」ことを実感する究極のアイテム。
AI三島由紀夫先生が語るサウナ!サウナは「肉体の試練」、そして「永遠なる美の具現」
「肉体は精神の神殿である」…三島由紀夫先生といえば、究極の肉体美と精神性の追求ですよね。彼がサウナに入ったら、もはや「ととのい」ではなく「修行」になることは想像に難くありません。
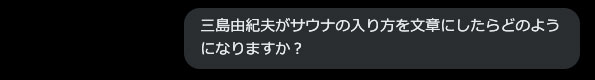
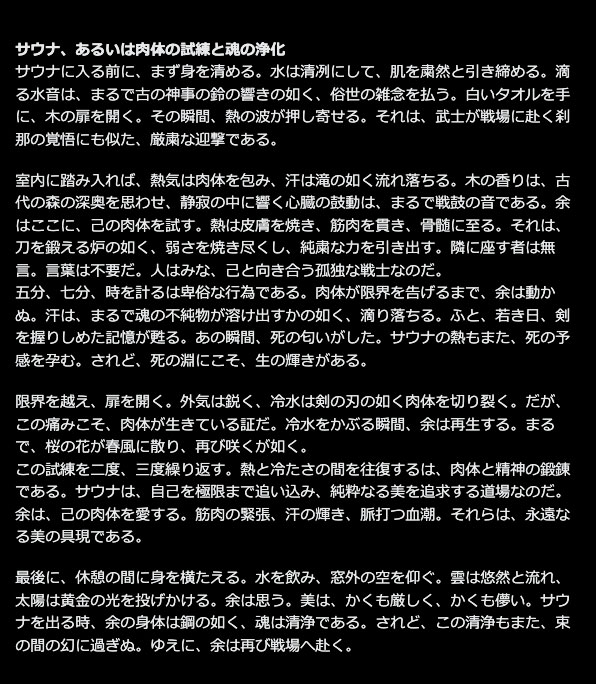
AI三島由紀夫先生、サウナに入る前の身を清める水は「清冽にして、肌を粛然と引き締める」って。水音は「古の神事の鈴の響きの如く、俗世の雑念を払う」って。もうサウナに行く前から神事ですよ。白いタオルを手に、木の扉を開く瞬間は「武士が戦場に赴く刹那の覚悟にも似た、厳粛な迎撃である」。う〜ん、分からん!
室内に踏み入ると「熱気は肉体を包み、汗は滝の如く流れ落ちる」。木の香りは古代の森の深奥を思わせ、心臓の鼓動はまるで戦鼓の音。もう耳に刀の音が聞こえてきそう。隣に座す者も無言で「人はみな、己と向き合う孤独な戦士なのだ」。サウナー全員、武士道精神習得の瞬間である。
そして「余はここに、己の肉体を試す」と宣言。余?熱は「皮膚を焼き、筋肉を貫き、骨髄に至る」って。いや、そこまでじゃなくない!?「刀を鍛える炉の如く、弱さを焼き尽くし、純粛な力を引き出す」。三島先生の美学が爆発しています。
「時を計るは卑俗な行為である」と、これまた潔い!「肉体が限界を告げるまで、余は動かぬ」。ストイックすぎ! 汗は魂の不純物が溶け出すって。デトックスの最終形態ですよ。若き日の「剣を握りしめた記憶」からの「死の匂いがした」…。サウナでそこまで哲学的になれるの、三島先生だけですよ。

限界を超えて冷水を浴びる。「冷水は剣の刃の如く肉体を切り裂く」。痛い!シングル水風呂かな!?でも「この痛みこそ、肉体が生きている証だ」と肯定。そして「余は再生する。まるで、桜の花が春風に散り、再び咲くが如く」。よく分からんけど壮大…。
この試練を繰り返すのは「肉体と精神の鍛錬」。「自己を極限まで追い込み、純粋なる美を追求する道場なのだ」と言い切る。もうサウナを精神道場にしてるんですもんね。「余は、己の肉体を愛する。筋肉の緊張、汗の輝き、脈打つ血潮。それらは、永遠なる美の具現である」。もうずっと「余」が気になる。ラオウやないか。でも、サウナでここまで肉体を賛美できるなんて、私も今日から自分の体をもっと愛でようと誓いました。
休憩中も哲学。「美は、かくも厳しく、かくも儚い」。サウナを出る時、「余の身体は鋼の如く、魂は清浄である」。そしてこの清浄も「束の間の幻」だから「ゆえに、余は再び戦場へ赴く」。三島由紀夫先生にとって、サウナは終わりのない美と戦いのループだったんですね。恐るべし。
AI三島由紀夫先生に学ぶサウナの極意
・サウナは戦場、水風呂は刀の刃だ!
・自分の肉体は最高の芸術作品。汗も輝きも愛でろ。
・痛みすら喜びに変える、ストイックな精神を持て!


