「銭湯を日本から消さない」、 ゆとなみ社の挑戦
こうした状況下で、ゆとなみ社は「銭湯を日本から消さない」をテーマに、銭湯の運営だけでなく、廃業寸前の銭湯の再生や、銭湯に関する様々な事業を手がける異色の企業だ。同社を「好きにやらせてくれる会社」と中村さんは表現する。
「銭湯を残すっていうテーマに沿ってれば結構何でもやる。全然他府県の銭湯へ手伝いに行くとかも。場合によってはそれを仕事として請け負うこともある」 。実際、人づての依頼で、大阪にある銭湯の風呂場の電気修理に駆け付けたこともあるという 。それはまるで、消えかけた銭湯の灯を、一つ一つ丁寧に再び灯していくかのようだ。
中村さん自身も、元々は別の仕事をしながらゆとなみ社の手伝いをしていた。「本業の仕事をしつつ、人が足りんくなったら駆り出されるみたいな。そんな携わり方を7年ぐらいやってました」。

きっかけは、9年前。「梅湯(京都の銭湯。ゆとなみ社が運営)でイベントで昔使っていた”のれん”をくれるという話を聞いて、『のれん欲しいんですけど』って梅湯に言いに行ったんです」 。しかし、のれんをもらうためには、「銭湯の掃除を10回する」という条件が。
「時給に換算したら全然割に合わないんですよ(笑)」と言いつつも、中村さんは掃除をやり遂げ、のれんを手に入れた。それをやり遂げた理由も「銭湯が好きということももちろんありますが、心のどこかで、仲間に入りたい、みんなとワイワイやりたいっていうのがあったんだと思います」と当時を振り返る 。
そして3年前、ついにゆとなみ社の一員として、銭湯経営に本格的に関わることになる。
「一般的な会社員の朝9時から夕方5時までの仕事が無理やなぁって思ってたんです。僕も前職はそうだったんですけど、もう無理で辞めました。それで、辞めて2日後ぐらいにゆとなみ社の湊三次郎(代表)から電話が来て、『銭湯の店長やらん?』みたいな。
僕も『じゃあやるわ』って返事して、その瞬間に一般企業の務めを諦めきれた感じがありました。なんて言うんですかね。普通の仕事は無理なんやろうなっていうモヤつきが、そう返事したことでやっと晴れた」 。
中村さんの言葉からは、銭湯への愛着と共に、自由な働き方を求める強い意志が感じられた。
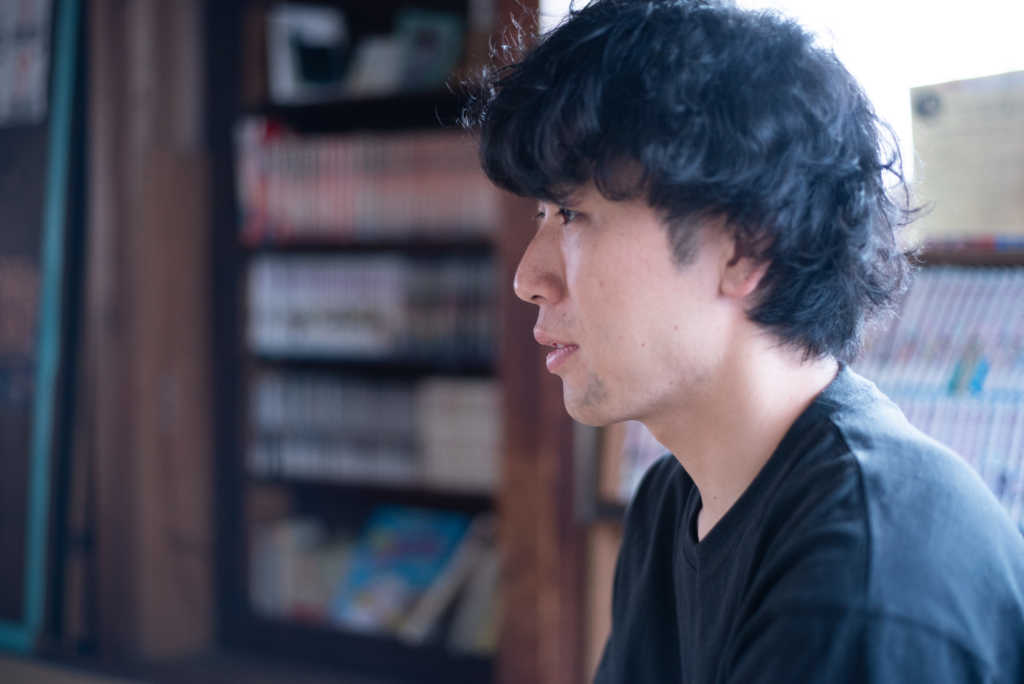
レトロと革新の融合。源湯の生き残り戦略
源湯もまた、例外なく時代の荒波に晒されている。築年数の古い建物は傾き、設備の老朽化も深刻だ。
「このままずっと使ったら、そのうちどっかのタイミングで大規模な”手入れ”をしないといけなくはなるのは決まってるんです」 。施設の老朽化は、多くの銭湯が直面する大きな課題だ。
ただ古いということを「レトロ」だと肯定しているだけでは生き残れない。源湯は、レトロな雰囲気を愛する人々に向けて積極的に情報を発信する一方で、アニメのモデルになるなど、若い世代にもアピール。CMにも登場するなど、メディアへの露出も増やしている。「若い世代にもっと銭湯を知ってもらいたい」という中村さんの想いがそこにはある 。

「実は源湯にはサウナもあるんですけど、壊れててずっと動かしてません。ちょっともう直せないレベルっていうか、直すってなったら新築にしないといけないレベルの話になるんで。なので、もう『ない』という方向でいこうって思って、今は『サウナない』っていうメッセージを入れたグッズを作ったりとか」 。
「ないなら無いでグッズ作ったらええやん」という発想の転換が、新たな価値を生み出す。グッズ販売にも力を入れ、客単価向上に繋げる戦略も奏功している。
「会社の方針ってほどではないですけど、やっぱ売り上げていくってなったら客単価を上げなければいけない。入浴料は決まってるんで、他のところでどう上げていくか。グッズ買ってもらえたらプラス何千円か売り上げが上がって客単価が上がっていくんで、一番上がりやすいんじゃないかなと思いますね」 。

銭湯は「居場所」。地域コミュニティの灯を守る
「銭湯は、ただお風呂に入るだけの場所じゃない」と中村さんは強調する。「特に若い子にとって、銭湯は地域の人との繋がりを感じられる、貴重な『居場所』なんです」 。実際、源湯は地域住民の交流の場として、なくてはならない存在となっている。
「若い人がここでダラダラしてくれてる思い出を残しときたいっていうのはあります」と中村さんは語る。自身も子どもの頃に銭湯に通っていた思い出があるという。

「小学校の時とか別に何か言われたわけでもなく、なんかただ近所のやつとチャリンコで銭湯に行ってたんですよ。もうその銭湯は廃業してしまっていますが、ふとした瞬間にその場所のことを思い出したりして懐かしいと思う一方で、その場所がもうなくなっているという寂しさもあります。
でも、そういう記憶が色んな人の中に残ってると、銭湯を残したいって思う人も出てくるのかなって思いますね。だから学生とかがここでダラダラしてくれて、記憶の中に残してくれることはめっちゃ嬉しいですね」 。
銭湯は、地域の人々にとって、単なる入浴施設ではない。番台では、常連客と従業員の何気ない会話が飛び交い、温かい雰囲気が漂う。そこには、人と人との繋がりがあり、世代を超えた交流が生まれる。源湯は、まさに地域コミュニティの核となっているのだ。



